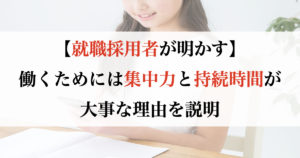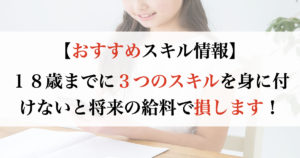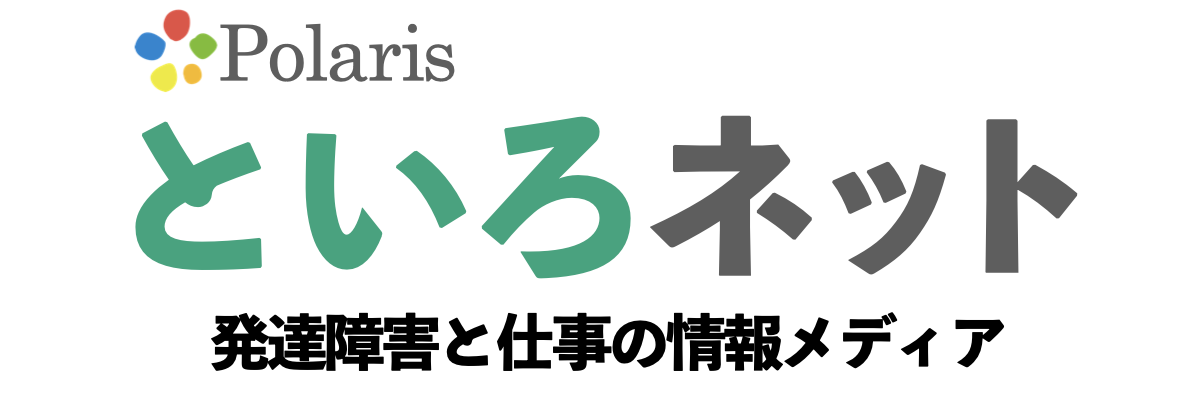それは人によって様々です。障害のある方の就労を提供しているところはたくさんあり、形態も違うんです。
そうなんだ!みんなが障害者雇用ってわけではないんだね。
もちろん障害者雇用で就職できるのが理想なんですが、体調や体力、障害の特性で就職が難しい方もいるんですよ。
そんなことはないですよ、そういう方が将来的に企業に就職できるように支援する福祉サービスもあるんです。
この記事で説明しますね!
現在、障害のある方の就労を提供する場として、企業の障害者雇用から就労支援事業所まで幅広くあり、業種も多種多様です。
また、現在、特別支援学校を卒業して就労をする人は全体の94%だと言われています。
ほとんどの支援学級の学生が高校を卒業してすぐに働くことを選択することになります。
今回は障害のある方の就労について記事をまとめたいと思います。
目次
障害者雇用(一般企業などに就職)
一般企業に障害者雇用枠として入社する形です。
合理的配慮を受けながら最低賃金以上のお給料と社会保障が適用されます。
現在では、会社の規模によって障害者枠を何人採用しなければいけないという決まりもあり、障害者雇用をする企業もかなり増えてきました。
あわせて読みたい【障害者雇用とは】一般雇用との違いと就職するのに必要なことを紹介!障害のある人の就職活動において、一般雇用での求人に頼るだけでは不利になってしまう場合や就労の機会を十分に得ることはできないのが現状です。そこで、企業や公的機...
就労継続支援A型
障害があり就職が困難な方に就労の機会を提供する福祉サービスです。
福祉サービスではありますが、事業所と雇用契約を結び最低賃金のお給料が支払われます。
あわせて読みたい【就労継続支援A型】働いてお給料がもらえる福祉サービス!障害があり、就労をしたいけれど就職するのが不安、困難である方の福祉サービスとして「就労継続支援A型」というサービスがあります。福祉サービスですが働くことができ...
就労継続支援B型
こちらも障害があり就職することが困難なかたに就労の機会を提供する福祉サービスです。
事業所との雇用契約がない分最低賃金の保障などはありませんが、自分のペースで無理なく働くことができ、働いた分の作業工賃が支払われます。
あわせて読みたい【就労継続支援B型】就労に自信がない方でも大丈夫!障害があり、就労をしたいけれど就職するのが不安、困難である方の福祉サービスとして「就労継続支援B型」というサービスがあります。福祉サービスですが働くことができ...
就労移行支援
2年間という利用期間の間で一般企業に就職するためのスキルを磨く場所です。
就労の訓練やビジネスマナー、ソーシャルスキルトレーニングなど働くことを学ぶための専門学校のようなサービスです。
あわせて読みたい【就労移行支援】「働くこと」に特化した専門学校?障害のある方が就職をする上でその手助けをしてくれる就労支援サービスには、「就労継続支援A型」や「就労継続支援B型」などがありますが、その中でも一定期間で企業へ...
就労準備型放課後等デイサービス
早期からの就労へ対する準備として最近増えてきている放課後等デイサービスです。
就労訓練をしたり、就労支援施設に体験実習に行ったり、就労移行のような要素がある放課後等デイサービスです。
https://toiro-net.jp/all/child/support-for-children-with-disabilities/houdei-5/25/
働くために必要なスキル

働くために大切なのは「集中力」をはじめ、通勤に関わる「自力移動」や働き続けるための生活習慣などの自己管理が必要になります。
これらのスキルは上記の就労支援施設がおこなう厚生労働省の「就労アセスメント」の項目にも大きく影響します。
こうしたスキルを早期から高めていく場所として最近の療育特化型の放課後等デイサービスの利用が有効になります。
あわせて読みたい【本当に重要】採用担当者から聞いた!就活までにして欲しい5つのこと発達障害のある子どもの将来を考えてると心配になることが多いと思います。特に就職のことは1番の悩みではないでしょうか?発達障害があるからといって就職できないわ...
あわせて読みたい【就職採用者が明かす】働くためには集中力と持続時間が大事な理由を説明子どもが18歳になり高校を卒業すると大学・専門学校、就職の選択をすることになりますね。企業採用担当者は採用をする際に判断するスキルがあるようです。このスキルは...
新しく増えつつある業種
最近の傾向として、IoT化によるテレワークやIT関係の障害者雇用が増えつつあり、就労移行などもプログラミングなどのパソコンやITスキルに特化しているところが増えてきています。
またAIやRPAの導入により従来のデータ入力やその他の事務仕事はAIやRPAがおこなうようになってきたので、そのAIやRPAをメンテナンスするエンジニアの仕事が増えつつあります。
あわせて読みたいこれからの企業の働くカタチ!場所や時間に縛られないテレワーク働くというと、自宅から職場に行き仕事をする。というイメージが多くあるかと思います。しかし、現在猛威を振るっているコロナウイルスの影響で外出による感染拡大が非...
まとめ
障害のある方の就労は様々な形態があり、個人の能力や体力などに合わせて働くことができます。
またそれをサポートする福祉サービスもありますので、お子さんの将来目指しているところに合わせて利用されるのもいいかと思います。
あわせて読みたい【おすすめ】18歳までに3つのスキルを身に付けないと将来の給料が減る障害のあるお子さんの将来に不安を抱えている方は多くいらっしゃるかと思います。「大人の発達障害」のように障害が軽ければ軽いほど健常者として見られることが多く、...